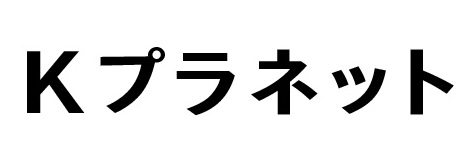山口県宇部市沖の海底炭鉱「長生炭鉱」では、太平洋戦争中の1942年2月3日に水没事故が発生し、日本人や朝鮮半島出身者を含む183人の作業員が犠牲となった。
特に、犠牲者の7割以上が朝鮮半島出身者であるとされる。
長年にわたり遺骨の収集活動を続けてきた市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」(井上洋子共同代表)は、今年8月下旬の潜水調査で頭蓋骨を含む人骨4点を発見した。
これを受けて同会は9月、東京都内で厚生労働省、外務省、警察庁の担当者に要請書を提出し、DNA鑑定による身元特定と遺族への迅速な遺骨返還、関係機関の役割の明確化、遺骨収集への支援を求めた。
国側は、戦没者遺骨収集推進法が定める「戦没者」に事故の犠牲者は当たらないとして、国による遺骨収集には従来通り消極的な姿勢を示している。
特に厚生労働省は、潜水調査の「安全性の懸念を払拭できていない」ことを理由に、国による収集や今後の潜水調査への財政支援についても否定的な考えを改めて示した。
一方で、警察庁の担当者はDNA鑑定を「やらないという話ではない」としつつ、技術的な調査が必要であると回答。
また、外務省は、多くの朝鮮半島出身者が犠牲となっていることから、韓国政府との情報交換や意思疎通を「できるだけ早く」行う方針を明らかにした。
井上共同代表は、遺骨発見から2週間が経過してもDNA鑑定が進んでいないことに「残念だ」と述べ、遺族が高齢であることから、政府に緊急性を持って問題に取り組むよう訴えている。
事故で父を亡くした遺族も、国が遺骨の収集と返還に重い腰を上げるべきだと訴えており、帝京大の浜井和史教授は、国がこれまでの姿勢を改める時期に来ていると指摘している。
(tysテレビ山口、読売新聞、yab山口ニュース、NHK 山口NEWS WEB 2025/9/10 配信)